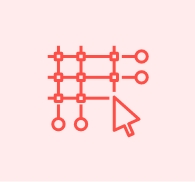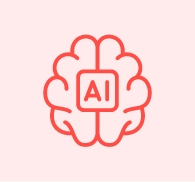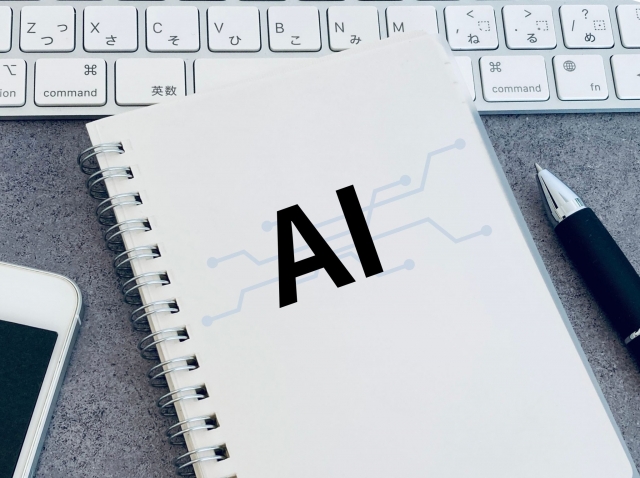当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
アパレルECサイトにおいて、売上を左右する最も重要な要素は「商品画像」です。魅力的な画像は顧客の購買意欲を高め、商品の価値を的確に伝えることで返品率の低下にも繋がります。
本記事では、コンバージョンを高める写真の7つの共通点をはじめ、撮影方法別のコツから加工テクニック、おすすめ機材までを網羅的に解説します。この記事を読めば、売れる商品画像の作り方をマスターし、ECサイトの成長を加速させることができます。
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
1. アパレルECサイトの売上は商品画像で決まる3つの理由
アパレルECサイトにおいて、商品画像は単なる商品の紹介写真以上の意味を持ちます。顧客が商品を直接手に取って確認できないオンラインの環境では、商品画像が顧客の五感に代わる唯一の情報源となるからです。魅力的な商品画像はサイトの第一印象を決定づけ、売上に直結する極めて重要な要素といえます。ここでは、なぜ商品画像がアパレルECサイトの売上を左右するのか、その3つの理由を具体的に解説します。
1.1 顧客の購買意欲を高める効果
質の高い商品画像は、顧客の「欲しい」という感情を直接的に刺激し、購買意欲をかき立てる強力な効果があります。人間が受け取る情報の約8割は視覚からと言われており、美しく、商品の魅力が最大限に伝わる写真は、テキストによる説明よりも遥かに早く、そして強く顧客の心に訴えかけます。
例えば、プロのモデルが商品を着用し、洗練されたコーディネートでライフスタイルを想起させるような写真は、顧客に「この服を着たら自分もこうなれるかもしれない」という憧れや期待感を抱かせます。その結果、商品のクリック率(CTR)やカート投入率の向上につながり、最終的なコンバージョンへと導くのです。
1.2 商品の価値と世界観を伝える役割
商品画像は、服そのもののデザインや色を伝えるだけでなく、ブランドが持つ独自の価値や世界観を表現するための重要なコミュニケーションツールです。写真のトーン&マナー、モデルの雰囲気、背景の選び方、光の使い方ひとつで、ブランドイメージは大きく変わります。例えば、高級感を打ち出したいブランドであれば、上質な空間で撮影し、重厚感のある色調で仕上げることで、商品の価格以上の価値を顧客に感じさせることができます。
逆に、親しみやすさをコンセプトにするブランドであれば、自然光を活かした明るく柔らかな雰囲気の写真で、顧客との心理的な距離を縮めることが可能です。このように、統一感のある商品画像を通じてブランドの世界観を一貫して伝えることは、顧客の共感を呼び、長期的なファンを育成するブランディングにおいて不可欠です。
1.3 返品率を低下させる情報提供
ECサイト運営における大きな課題の一つが、「イメージと違った」「サイズが合わなかった」といった理由による返品です。商品画像は、こうした購入後のミスマッチを防ぎ、返品率を低下させるための正確な情報を提供するという重要な役割を担っています。例えば、生地の質感がわかるように素材をアップで撮影した写真や、ボタンやステッチなどのディテールが鮮明にわかる写真、そして商品の色味を実物に限りなく近づけた写真は、顧客が抱く購入前の不安を解消します。
さらに、様々な角度から撮影した写真や、モデルの身長・着用サイズを明記したコーディネート写真を用意することで、顧客は着用した際のシルエットやサイズ感をより具体的にイメージできます。正確で多角的な情報提供は顧客満足度を高め、結果として返品に伴うコストや手間の削減にもつながるのです。
2. コンバージョン率を高めるアパレル商品画像7つの共通点
多くのECサイトで売上を伸ばしているアパレル商品には、顧客の購買意欲を掻き立てる写真に共通点が存在します。ここでは、コンバージョン率の向上に直結する7つの重要なポイントを解説します。自社サイトの商品写真がこれらの要素を満たしているか、確認しながらご覧ください。
2.1 全身のコーディネートがわかる
顧客が最も知りたい情報の一つは、「その服を実際に着たときにどのように見えるか」です。トップス単品の写真だけでは、ボトムスとのバランスや全体のシルエットを想像するのは困難です。モデルが着用した全身のコーディネート写真を用意することで、顧客は着用シーンを具体的にイメージでき、購入へのハードルが大きく下がります。
また、コーディネートで合わせた他の商品をサイト内で提案することにより、合わせ買い、いわゆるクロスセルを促進する効果も期待できます。モデルの身長と着用サイズを併記することで、顧客は自分自身の体型と照らし合わせやすくなり、より安心して購入を検討できるようになります。
2.2 商品のディテールが鮮明
オンラインショッピングでは、商品を直接手に取って確認することができません。そのため、ECサイトの商品画像は、実店舗における「商品を手に取る」行為の代替となる重要な役割を担います。ボタンのデザイン、ステッチの縫製、生地の織り方、ブランドロゴの刺繍といった細部(ディテール)が鮮明に写っている写真は、商品の品質を雄弁に物語り、顧客に安心感と信頼を与えます。
特に、価格帯の高い商品ほど、ディテールへのこだわりが購入の決め手となるケースは少なくありません。ズームしても画質が荒くならないよう、高解像度で撮影されたクローズアップ写真を複数枚用意することが不可欠です。
2.3 素材感が伝わる
アパレル商品において、デザインや色と同じくらい重要なのが「素材感」です。写真から生地の柔らかさ、厚み、光沢感、透け感などが伝わることで、顧客は着心地や季節感を把握できます。例えば、リネンであれば特有のシャリ感を、カシミヤであれば滑らかな質感を、写真で表現することが求められます。
素材感を効果的に伝えるには、自然光や適切なライティングを活用し、生地のテクスチャが際立つように撮影するのがコツです。「イメージと素材が違った」という理由での返品は非常に多いため、素材感が伝わる写真は返品率の低下にも直接的に貢献します。
2.4 様々な角度からの写真がある
顧客は、購入を検討している商品をあらゆる角度から確認したいと考えています。正面からの写真だけでなく、バックスタイル、サイドからのシルエット、斜めからの見え方など、多角的な情報を提供することが顧客の不安を取り除き、購入の後押しとなります。特に、デザイン性の高い商品や、シルエットに特徴のある衣類では、多角的な写真の重要性はさらに増します。
最低でも、正面、背面、側面の3カットは必須と考え、商品によってはさらに多くの角度からの写真を用意しましょう。これにより、顧客はオンラインでありながら、まるで商品を手に取って眺めているかのような体験を得ることができます。
2.5 ブランドイメージと統一感がある
優れた商品画像は、個々の商品を魅力的に見せるだけでなく、サイト全体でブランドの世界観を構築します。写真の明るさや色味、背景、モデルの雰囲気、構図などに一貫性を持たせることで、顧客に洗練された印象を与え、ブランドへの信頼と愛着を育みます。
例えば、ミニマルでクリーンなブランドであれば白背景を基調とし、ナチュラル系のブランドであれば自然光や植物を取り入れるなど、ブランドコンセプトに沿った写真撮影のレギュレーションを設けることが有効です。統一感のある美しいビジュアルは、リピート購入を促す強力なブランディング要素となります。
2.6 サイズ感がイメージしやすい
アパレルECにおける最大の課題は「サイズ感の伝わりにくさ」です。この課題を解決する写真は、コンバージョン率を飛躍的に向上させます。モデルが着用している写真に、モデルの身長と着用サイズ(例:「モデル身長: 165cm / 着用サイズ: M」)を必ず記載しましょう。
さらに、同じ商品で身長の異なる複数のモデルを起用したり、S・M・L各サイズの着用感を比較できる写真を用意したりすることも非常に効果的です。また、バッグや小物であれば、スマートフォンやペットボトルなど、誰もが大きさを知っているものと一緒に撮影することで、顧客は直感的にサイズを把握できます。
2.7 使用シーンが想像できる
単に商品を平置きした写真だけでは、顧客はその商品を「自分ごと」として捉えにくい場合があります。顧客がその服を着てどこへ出かけ、どのような時間を過ごすのか、具体的な使用シーンを想像させる「ライフスタイル写真」は、購買意欲を強く刺激します。
例えば、オフィスカジュアルのブラウスであればオフィス街で、リゾートワンピースであれば海辺で撮影するなど、商品の特性に合わせたロケーション撮影が有効です。これにより、顧客は商品を所有した後のポジティブな未来をイメージし、「この服が欲しい」という感情的な動機付けがなされ、購入へと繋がりやすくなります。
3. 撮影方法別アパレル商品画像の撮り方とコツ
アパレルECサイトの商品撮影には、大きく分けて「モデル撮影」「トルソー撮影」「置き画撮影」の3つの方法が存在します。それぞれにメリット・デメリットがあり、表現できる世界観や伝えられる情報が異なります。ブランドのコンセプトやターゲット層、そして予算に応じてこれらの撮影方法を適切に選択、あるいは組み合わせることが、売上向上の鍵となります。ここでは、それぞれの撮影方法の特徴と、魅力を最大限に引き出すための具体的なコツを解説します。
3.1 モデル撮影でブランドの世界観を表現する
モデルが実際に商品を着用して撮影する方法は、アパレルECサイトにおいて最も訴求力の高い撮影手法の一つです。顧客が着用した際のイメージを具体的に想像できるため、購買意欲を直接的に刺激する効果が期待できます。ブランドが目指すライフスタイルや世界観を表現するのに最適ですが、その分コストや準備に手間がかかる側面もあります。
〇ブランドイメージに合ったモデルを選ぶ
モデルの選定は、ブランドイメージを決定づける非常に重要な要素です。ターゲットとなる顧客層と年齢や雰囲気が近いモデルを起用することで、顧客は商品を「自分ごと」として捉えやすくなります。例えば、20代向けのカジュアルブランドであれば親近感のあるモデル、ハイブランドであればクールで洗練された雰囲気のモデルといったように、ブランドコンセプトとの一貫性を最優先に考えましょう。
〇動きのあるポージングで躍動感を出す
ただ直立しているだけの写真では、商品の魅力は十分に伝わりません。歩く、振り返る、軽くジャンプするなど、動きのあるポージングを取り入れることで、服のドレープや素材の揺れ感が表現され、写真に躍動感が生まれます。スカートの広がりやジャケットの着心地など、静止画だけでは伝わりにくい機能的な側面もアピールできます。
〇ロケーション撮影でストーリー性を加える
スタジオでの白背景撮影だけでなく、商品のコンセプトに合ったロケーションで撮影を行うことで、写真にストーリー性が生まれます。例えば、リゾートワンピースであれば海辺で、オフィスカジュアルであればお洒落なカフェや街中で撮影することで、顧客は具体的な着用シーンをより鮮明にイメージできます。これにより、商品の利用シーンが広がり、購入後の満足度を高める効果も期待できます。
〇顔を写さない撮影のテクニック
あえてモデルの顔を写さず、首から下や後ろ姿を中心に撮影する手法も有効です。これにより、顧客はモデルのイメージに左右されることなく、自分自身が着用した姿を投影しやすくなります。また、商品そのものに視線を集中させたい場合や、様々なコーディネートで同じモデルを起用する際に、汎用性が高まるというメリットもあります。
3.2 トルソー撮影でコストを抑えつつ質を担保する
トルソー(マネキン)に商品を着用させて撮影する方法は、モデル撮影に比べてコストを大幅に抑えながら、商品の形状を立体的に美しく見せられるバランスの取れた手法です。特に、商品のシルエットやデザインを正確に伝えたい場合に適しており、ECサイト全体で写真のクオリティに統一感を出しやすいというメリットがあります。
〇商品の魅力を引き出すトルソーの選び方
トルソーには、首のあるタイプやないタイプ、腕の有無、素材(布張り、樹脂製など)、色(白、黒、グレーなど)といった様々な種類があります。例えば、ネックレスなどアクセサリーも合わせて見せたい場合は首ありタイプ、商品のイメージを邪魔したくない場合はシンプルな首なしタイプが適しています。ブランドのテイストや商品の色味に合わせて、最も魅力的に見えるトルソーを選びましょう。
〇「ゴーストマンネキン」で着用イメージをリアルに
ゴーストマンネキン(インビジブルマンネキン)とは、撮影後に画像加工でトルソーを消し、あたかも透明人間が服を着ているかのように見せる合成技術です。この手法を用いることで、トルソーを使わずに商品の立体的な形状やフィット感をリアルに表現できます。また、襟元の内側にあるブランドタグや裏地のデザインまで見せることが可能になり、顧客に与える情報量が格段に増えます。
〇アイロンがけと着付けを丁寧に行う
トルソー撮影で最も重要なのが、撮影前の準備です。商品に少しでもシワやヨレがあると、それだけで安っぽい印象を与えてしまいます。撮影前には必ずスチームアイロンで丁寧にシワを伸ばし、商品のラインが最も美しく見えるように着付けを行いましょう。必要に応じて、商品の内側に詰め物をしたり、背面をピンやクリップで留めたりして、理想的なシルエットを作り出すことがクオリティ向上のポイントです。
3.3 置き画撮影で手軽に正確な商品情報を伝える
置き画(平置き)撮影は、商品を床やテーブルなどの平面に置いて真上から撮影する方法です。モデルやトルソーが不要なため、最も手軽でコストを抑えられる撮影手法と言えます。商品の色やデザイン、ディテールを正確に伝えやすく、小物と組み合わせることでお洒落な雰囲気も演出しやすいため、SNSでの発信とも相性が良いのが特徴です。
〇背景選びで商品の印象をコントロールする
背景は商品の印象を大きく左右します。ECサイトの基本である白背景は、商品をクリーンに見せ、色味を正確に伝えるのに適しています。その他にも、木目調の背景はナチュラルで温かみのある雰囲気を、コンクリートや大理石調の背景はモダンで洗練された印象を与えます。背景紙や布、リメイクシートなどを活用し、ブランドイメージや商品のコンセプトに合わせて背景を選びましょう。
〇光と影を意識して立体感を演出する
置き画撮影は平面的になりがちですが、ライティングを工夫することで立体感を出すことが可能です。真上からのフラットな光だけでなく、サイドから自然光や照明を当てることで、生地の織り目や素材の質感を際立たせる自然な影が生まれます。これにより、写真に奥行きが生まれ、商品の魅力をより深く伝えることができます。
〇小物を効果的に使ってコーディネートを提案する
トップスを撮影する際にボトムスや靴を合わせたり、ワンピースにバッグやアクセサリーを添えたりと、小物を効果的に配置することで、単なる商品紹介ではなくコーディネート提案ができます。これにより、顧客は購入後の着回しをイメージしやすくなります。ただし、あくまで主役は商品です。小物を使いすぎると情報過多になり、商品が目立たなくなるため、バランスを考えて配置することが重要です。
〇商品の畳み方や配置にこだわる
商品をどのように置くかによって、写真のクオリティは大きく変わります。Tシャツであればきれいに畳んで誠実な印象を与えたり、ニットであればあえて無造作に置いて柔らかい雰囲気を演出したりと、商品の特性に合わせた置き方を工夫しましょう。袖を少し曲げたり、裾に動きをつけたりするだけでも、写真が生き生きとした印象になります。グリッド線を意識した構図や、S字カーブを意識した配置なども、バランスの取れた美しい写真を作るテクニックです。
4. これだけは押さえたいECサイト向け商品画像の加工テクニック
アパレルECサイトにおいて、撮影しただけの「撮って出し」の写真をそのまま使用することは推奨されません。顧客が商品を直接手に取れないECサイトでは、写真のクオリティが商品の魅力を左右し、売上に直結するためです。ここでは、ECサイトの商品画像に必須となる基本的な加工テクニックについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
4.1 基本のレタッチ 明るさ・彩度・コントラスト
レタッチは、撮影した写真の印象を決定づける重要な工程です。特に「明るさ」「彩度」「コントラスト」の3つを調整するだけで、商品の見栄えは劇的に改善します。これらの基本的な調整は、顧客に商品の魅力を的確に伝えるための第一歩です。
〇明るさ・露出補正で商品の魅力を引き出す
ECサイトの商品画像は、少し明るめに調整するのが基本です。写真が暗いと、商品が古びて見えたり、安っぽい印象を与えたりする可能性があります。また、暗い画像では商品のディテールや素材感が伝わりにくくなります。露出補正機能を使って画像全体を明るくすることで、清潔感や洗練された雰囲気を演出し、商品の細部までクリアに見せることができます。ただし、明るくしすぎると白飛びしてしまい、生地の質感や色が失われるため、細部が潰れない範囲で調整することが重要です。
〇コントラスト調整でメリハリをつける
コントラストは、画像の明るい部分と暗い部分の差を調整する機能です。コントラストが低いと、全体的にぼんやりとした眠い印象の写真になってしまいます。一方、コントラストを適度に高めることで、写真にメリハリが生まれ、商品の輪郭やデザインがくっきりと際立ちます。特に、柄物のアイテムや異素材を組み合わせたデザインの場合、コントラストを調整することで、それぞれの要素が引き立ち、より魅力的に見せることが可能です。
〇彩度を調整して鮮やかな色合いに
彩度は、色の鮮やかさを調整する項目です。撮影環境によっては、実際の色よりもくすんで写ってしまうことがあります。彩度を少し上げることで、商品の持つ本来の鮮やかな色合いを表現し、顧客の目を引くことができます。ただし、彩度を上げすぎると、色が飽和してしまい、不自然で安っぽい印象になるだけでなく、実物との色差が大きくなる原因にもなります。あくまで自然な範囲で、商品の魅力が増すように微調整することを心がけましょう。
4.2 商品の色を忠実に再現する色調補正
ECサイトにおける返品理由の上位に常に挙げられるのが、「商品の色がイメージと違った」というものです。この問題を解決するためには、商品の色を可能な限り実物に近づける「色調補正」が不可欠です。特にホワイトバランスの調整は、正確な色再現のための基本となります。
〇ホワイトバランスの調整で正確な色味を表現
ホワイトバランスとは、撮影した写真の色かぶりを補正し、本来の「白」を正しく表現するための機能です。例えば、白熱電球の下で撮影すると全体的にオレンジがかった写真に、日陰で撮影すると青みがかった写真になりがちです。画像編集ソフトのホワイトバランス調整機能を使用し、写真の中の「白」や「グレー」の部分を基準に設定することで、環境光による色かぶりを取り除き、商品本来の色を正確に再現することができます。これにより、顧客が抱く色のイメージと実物とのギャップを最小限に抑えることが可能になります。
〇不要物の除去とトリミング
プロの現場では、撮影時に付着してしまったホコリや糸くず、背景の汚れなどを丁寧に除去する作業も行います。こうした小さなノイズを取り除くことで、商品の清潔感と品質の高さをアピールできます。Adobe Photoshopの「スポット修復ブラシツール」などを使えば、簡単かつ綺麗に不要物を消すことが可能です。また、トリミング(切り抜き)によって構図を整えることも重要です。商品が中央にバランス良く配置されるように余白を調整したり、複数の商品画像を同じサイズ・比率で統一したりすることで、サイト全体に整然とした印象を与え、顧客が快適に商品を閲覧できるようになります。
4.3 売上を伸ばすための応用編集テクニック
基本的なレタッチと色調補正に加え、もう一歩踏み込んだ編集テクニックを導入することで、競合サイトと差別化し、さらにコンバージョン率を高めることができます。ここでは、特に効果的な「白抜き加工」と「リサイズ」について解説します。
〇白抜き・背景切り抜きで商品に集中させる
白抜きとは、商品の背景を完全に白くする加工のことです。背景に余計な情報がなくなることで、顧客の視線は自然と商品そのものに集中します。これにより、商品の形やデザインが明確に伝わりやすくなります。特に、Amazonや楽天市場といった大手ECモールでは、メイン画像に白抜きを推奨、あるいは義務付けている場合が多く、出店する上では必須のテクニックと言えるでしょう。また、背景を切り抜いておくことで、特集ページやバナー広告など、様々な用途に画像を二次利用しやすくなるというメリットもあります。
〇Web表示に最適化するリサイズと圧縮
デジタルカメラで撮影した高画質な画像は、ファイルサイズが非常に大きくなりがちです。サイズの大きな画像をそのままECサイトにアップロードすると、ページの表示速度が著しく低下し、ユーザーの離脱に繋がってしまいます。これを防ぐために、Web表示に適したサイズに「リサイズ(画像の寸法を小さくする)」し、画質を損なわない範囲で「圧縮(ファイルサイズを軽くする)」する作業が必要です。画像の横幅を1000〜1500ピクセル程度に統一し、JPEG形式で適切に圧縮することで、ページの表示速度と画像のクオリティを両立させることができます。 当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
5. アパレル商品画像の撮影機材とツールの選び方
高品質な商品画像を用意するためには、撮影機材と編集ツールの選定が欠かせません。しかし、高価な機材を揃えなければならないというわけではなく、近年ではスマートフォンでも工夫次第で魅力的な写真を撮影できます。ここでは、ECサイトの規模や目指すクオリティに応じて、最適な機材とツールを選ぶためのポイントを解説します。
5.1 スマホ撮影で揃えたい便利グッズ
スマートフォンのカメラは年々高性能化しており、手軽にECサイト用の商品画像を撮影する上で強力なツールとなります。ただし、スマホ単体での撮影には限界があるため、いくつかの便利グッズを揃えるだけで写真のクオリティを飛躍的に向上させることが可能です。ここでは、最低限揃えておきたいアイテムをご紹介します。
〇三脚
手持ちでの撮影は手ブレの原因となり、写真がぼやけてしまうことがあります。特に室内での撮影では光量が不足しがちで、シャッタースピードが遅くなるため手ブレしやすくなります。三脚を使ってスマートフォンを固定することで、手ブレを完全に防ぎ、シャープで鮮明な写真を撮影できます。また、同じアングルから複数の商品を撮影する際にも構図が安定するため、サイト全体に統一感が生まれます。
〇レフ板
レフ板は、光を反射させて被写体の暗い部分や影を明るくするための板です。自然光や照明の光をレフ板で反射させ、影になっている部分に当てることで、商品のディテールがより鮮明に見えるようになります。特にアパレル商品では、服のドレープや素材の質感を表現する上で非常に効果的です。専用のレフ板でなくても、白い画用紙やスチレンボードなどで代用することも可能です。
〇照明(LEDライト)
天候に左右されず、安定した光を確保するためには照明機材が役立ちます。家庭用の照明だけでは光量が足りなかったり、光の色味が商品本来の色と異なって見えたりすることがあります。撮影用に販売されているリングライトや小型のLEDライトを用意すれば、いつでも明るくクリアな写真を撮影できます。光の当てる角度を調整することで、商品の立体感や素材感をコントロールすることも可能です。
〇背景紙・背景布
商品の魅力を引き立て、ブランドの世界観を演出するためには背景が重要です。背景紙や背景布を使えば、生活感のある背景を隠し、商品だけに集中させることができます。ECサイトでは、商品の色を正確に伝えるために白やグレーの背景が一般的に使われますが、ブランドイメージに合わせて木目調やコンクリート調の背景シートを使うのも効果的です。シワになりにくい素材を選ぶと、撮影後の編集の手間を省けます。
5.2 本格的な撮影に必要なカメラとレンズ
より高いクオリティを追求し、ブランドイメージを確立したい場合は、デジタル一眼カメラの導入を検討しましょう。スマートフォンと比較して、画質の精細さ、背景のボケ感、色の再現性など、表現の幅が大きく広がります。ここでは、本格的な撮影に必要となるカメラ本体やレンズの選び方について解説します。
〇カメラ本体(ミラーレス一眼・デジタル一眼レフ)
本格的な撮影には、レンズ交換が可能なミラーレス一眼カメラかデジタル一眼レフカメラがおすすめです。近年では、小型・軽量で高性能なミラーレス一眼カメラが主流となっています。電子ビューファインダーで撮影後の仕上がりを確認しながら撮影できるため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。ソニーのαシリーズやキヤノンのEOS Rシリーズなどが人気を集めています。予算や求める機能に応じて、最適な一台を選びましょう。
〇交換レンズ(単焦点・ズーム・マクロ)
カメラ本体以上に写真のクオリティを左右するのがレンズです。レンズを使い分けることで、多彩な表現が可能になります。
まず、一本で幅広い画角をカバーできる「標準ズームレンズ」は、コーディネート撮影から商品のアップまで対応できるため非常に便利です。
背景を美しくぼかして商品を際立たせたい場合は、「単焦点レンズ」が最適です。F値(絞り)が小さい明るいレンズが多く、少ない光でも明るく撮影できるメリットもあります。
アクセサリーやボタン、生地の織り目といった細かいディテールを大きく写したい場合には、「マクロレンズ」が必要になります。
〇本格的な照明機材(ストロボ・ソフトボックス)
プロ品質のライティングには、ストロボ(フラッシュ)が欠かせません。太陽光のような強力な光を瞬間的に発光させることで、シャープでクリアな画像を撮影できます。ストロボの光は非常に硬いため、「ソフトボックス」や「アンブレラ」といったアクセサリーを装着して光を拡散させ、柔らかく自然な光を作り出すのが一般的です。これにより、商品の素材感を損なうことなく、美しく見せることができます。
5.3 無料で使えるおすすめ画像編集ソフト
撮影した写真は、そのままECサイトに掲載するのではなく、編集・加工を行うことでさらに魅力的になります。明るさや色の調整、不要な写り込みの除去といったレタッチ作業は、商品の価値を高める上で非常に重要です。高価な有料ソフトもありますが、まずは無料で使えるツールから始めてみることをおすすめします。
〇PC向け編集ソフト
パソコンでじっくりと編集作業を行いたい場合は、高機能な無料ソフトが選択肢となります。 代表的なものに「GIMP(ギンプ)」があります。有料ソフトのAdobe Photoshopに匹敵するほどの多彩な機能を備えており、本格的なレタッチや合成が可能です。多機能な分、操作に慣れが必要ですが、使いこなせればプロレベルの画像編集が実現できます。
また、ブラウザ上で手軽に使える「Canva(キャンバ)」も人気です。直感的な操作でトリミングや明るさ調整ができ、豊富なテンプレートを使ってバナー画像なども簡単に作成できます。
〇スマートフォン向け編集アプリ
撮影から編集までをスマートフォンで完結させたい場合は、編集アプリを活用しましょう。 Googleが提供する「Snapseed(スナップシード)」は、指先で直感的に操作できる高機能なアプリです。写真全体だけでなく、明るくしたい部分だけを部分的に補正することも可能です。
Adobeが提供する「Lightroom Mobile(ライトルーム モバイル)」も非常に強力なツールです。特に色調補正機能が優れており、商品の色を忠実に再現したい場合に役立ちます。無料版でも基本的な編集機能は十分に利用できます。
6. まとめ
アパレルECサイトの競争が激化する中で、売上を大きく左右するのが商品画像です。顧客は実物を手に取れないため、画像を頼りに購入を判断します。魅力的な画像は購買意欲を高めるだけでなく、商品の価値を正確に伝え、返品率の低下にも繋がります。
今回は、売れる商品画像に共通する7つのポイントから、モデル・トルソー・置き画といった撮影方法別のコツ、加工テクニックまでご紹介しました。この記事を参考に、ぜひ自社サイトの商品画像を見直し、売上アップを目指してください。
当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
それではまた。
アンドファン株式会社
中小企業診断士 田代博之