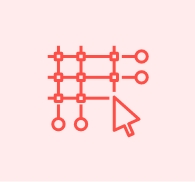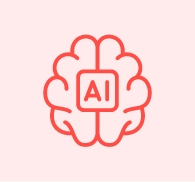当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
国内市場の成熟化を背景に、海外へ販路を拡大できる越境ECを検討する企業は増加しています。しかし、十分な準備なしに参入し「思ったように儲からない」と悩むケースも少なくありません。その失敗の多くは、データに基づいた戦略や現地への最適化不足が原因です。
本記事では、越境ECのよくある失敗原因を分析し、売上を倍増させるための具体的な解決策だけでなく、初心者でも失敗しないための始め方まで網羅的にご紹介します。
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
そもそも越境ECとは?基礎知識と市場の将来性
国内のEC市場が成熟期を迎えつつある中、新たな成長戦略として多くの企業が注目しているのが「越境EC」です。越境ECとは、国境を越えて行われる電子商取引(Eコマース)のことを指します。具体的には、日本の事業者がインターネット上のECサイトを通じて、海外の消費者に向けて商品を販売するビジネスモデルです。
国内の消費者だけをターゲットにするのではなく、世界中の人々を顧客とすることで、事業者はこれまでになかった大きなビジネスチャンスを掴むことが可能になります。特に、高品質で信頼性の高い日本製品は海外でも人気が高く、インバウンド需要が落ち着いた後も、海外からの購入意欲は依然として高い水準にあります。本章では、越境ECの基本的な仕組みと、その驚異的な成長を続ける市場の将来性について詳しく解説します。
1.1 越境ECの仕組みをわかりやすく解説
越境ECの仕組みは、国内のECと基本的には同じですが、「国境を越える」という点においていくつかの特有の要素が加わります。その流れは、大きく分けて「注文」「決済」「物流」の3つのステップで構成されています。
まず、海外の消費者が日本の事業者が運営するECサイトにアクセスし、商品を注文します。この際、サイトが多言語に対応していることが、消費者の購入のハードルを下げる上で極めて重要です。次に、注文された商品の代金を支払う「決済」のステップです。海外の消費者が日常的に利用しているクレジットカードブランドや、PayPal、Alipayといったオンライン決済サービスなど、現地の主要な決済手段を導入しておく必要があります。
決済が完了すると、商品を海外の購入者へ届ける「物流」のステップに移ります。商品は国内の倉庫で梱包され、国際スピード郵便(EMS)や国際宅配便(DHL、FedExなど)といった国際配送サービスを利用して発送されます。このとき、商品を輸出入する際に発生するのが「関税」です。関税の取り扱いや通関手続きは複雑なため、専門の配送業者や代行サービスと連携することが一般的です。これらの「言語」「決済」「物流」「関税」といった海外取引特有の課題をクリアすることで、国内ECと同じようにスムーズな商取引が実現します。
1.2 拡大を続ける世界の越境EC市場規模
越境ECの市場規模は、世界的に見ても驚異的なスピードで拡大を続けています。経済産業省が発表している報告書によると、世界の越境EC市場規模は年々増加しており、今後も高い成長率で推移すると予測されています。この成長の背景には、世界的なインターネットとスマートフォンの普及、SNSを通じたグローバルな情報共有、そして各国の消費者がより多様で高品質な商品を求めるようになったことなどが挙げられます。
特に、巨大な人口を抱える中国や、EC市場が急速に発展している東南アジア諸国は、日本の事業者にとって非常に魅力的な市場です。また、北米やヨーロッパにおいても、日本の伝統工芸品、アニメや漫画の関連グッズ、最新の化粧品など、特定のカテゴリーにおいて高い需要が存在します。実際に、日本の事業者から商品を購入している国の上位には、中国やアメリカが常に名を連ねており、日本製品への根強い人気と信頼がうかがえます。
国内市場の人口減少や少子高齢化が進む中、海外に活路を見出すことは、多くの企業にとって持続的な成長を達成するための重要な鍵となります。このように、拡大を続けるグローバル市場に直接アプローチできる越境ECは、事業規模の大小を問わず、すべての事業者にとって無視できない大きな可能性を秘めているのです。
越境ECのメリットと知っておくべきデメリット
海外市場への挑戦は、国内のビジネスだけでは得られない大きな可能性を秘めています。しかし、その一方で、国内ECにはない特有の課題やリスクが存在することも事実です。越境ECへの参入を成功させるためには、これらのメリットとデメリットを事前に正確に把握し、十分な対策を講じることが不可欠です。ここでは、事業者が享受できる恩恵と、直面する可能性のある課題について具体的に解説します。
2.1 メリット 海外への販路拡大と売上アップ
越境ECに取り組む最大のメリットは、国内市場の枠を超えて、世界中の消費者をターゲットにできる点にあります。これにより、ビジネスの成長を飛躍的に加速させることが可能です。
少子高齢化により国内市場の縮小が懸念される中、海外に目を向けることで新たな顧客層を獲得し、事業の持続的な成長基盤を築くことができます。インターネットを通じて、これまでアプローチできなかった国や地域の人々に自社の商品を届けられるのは、越境ECならではの強みです。
特に「Made in Japan」製品は、その品質の高さや信頼性から、海外で高いブランド価値を確立しています。アニメやゲームといったポップカルチャー関連商品、高品質な化粧品、精密な文房具、伝統的な工芸品などは、特定の国や地域で熱狂的なファンを獲得しており、高い需要が見込めます。また、昨今の円安は海外の消費者にとって日本の商品が割安に購入できる追い風となっており、販売機会の拡大に直結しています。
さらに、実店舗を海外に構える場合に比べて、ECサイトであれば比較的低コストかつスピーディーに海外展開を開始できる点も大きな魅力です。これにより、中小企業や個人事業主であっても、世界を舞台にしたビジネスに挑戦しやすくなっています。
2.2 デメリット 参入前に把握すべき注意点と課題
大きなリターンが期待できる越境ECですが、成功のためには乗り越えるべきいくつかのハードルが存在します。これらのデメリットや課題を軽視すると、予期せぬトラブルやコスト増につながるため、事前の理解と準備が欠かせません。
まず直面するのが「言語・文化の壁」です。Webサイトや商品説明を単に翻訳するだけでは、商品の魅力は十分に伝わりません。現地の文化や生活習慣、宗教などを理解し、消費者の心に響く表現を用いる「ローカライゼーション」が求められます。また、問い合わせやクレーム対応も現地の言語で行う必要があり、カスタマーサポート体制の構築が重要な課題となります。
次に「法律・規制への対応」が挙げられます。国によって関税の仕組み、輸入が禁止・制限されている品目、製品の表示義務などが大きく異なります。特にEUのGDPR(一般データ保護規則)に代表されるような個人情報保護法への対応は必須です。これらの法規制を遵守しなければ、商品の没収や罰金の対象となるリスクがあります。
「物流・決済システム」も大きな課題です。国際配送は国内配送に比べて送料が高額になり、配送日数も長くなる傾向があります。また、配送中の破損や紛失、通関での遅延といったトラブルも想定しなければなりません。決済に関しても、日本ではクレジットカードが主流ですが、国によってはPayPalやAlipay、WeChat Payといった特定の電子決済サービスが好まれるため、ターゲット国に合わせた多様な決済手段の導入が必要です。
その他にも、為替レートの変動によって売上や利益が左右される「為替変動リスク」や、国内での成功体験が通用しない「海外向けプロモーションの難しさ」など、越境EC特有の課題が数多く存在します。これらの課題に一つひとつ着実に対応していくことが、成功への鍵となります。
なぜあなたの越境ECは儲からないのか?よくある失敗原因を徹底分析
国内市場の成熟化や円安を背景に、多くの企業が新たな成長機会を求めて越境ECに参入しています。しかし、「海外で販売すれば売れるはず」といった安易な期待だけで始めてしまい、思うような成果を出せずに撤退するケースも少なくありません。成功への近道は、まず失敗の原因を正しく理解することです。ここでは、多くの事業者が陥りがちな5つの典型的な失敗原因を深掘りし、あなたのビジネスがなぜ儲からないのかを徹底的に分析します。
3.1 原因1 戦略なき海外展開
越境ECで最も多い失敗が、明確な戦略を持たずに事業を開始してしまうケースです。国内で成功したビジネスモデルや商品を、そのまま海外に持ち込むだけで成功するほど、海外市場は甘くありません。事前のリサーチや計画が不十分なままでは、暗闇の中を手探りで進むようなものです。
具体的には、「どの国で、誰に、何を売るのか」という事業の根幹が曖昧なまま進めてしまうことが挙げられます。市場規模や成長性、競合の状況、法規制といったマクロな視点での市場調査を怠り、漠然としたイメージだけでターゲット国を選定してしまうのです。
また、ターゲット顧客のペルソナ(年齢、性別、所得、ライフスタイルなど)が不明確なため、商品の選定や価格設定、プロモーションのすべてが的外れになってしまいます。売上や利益率といった具体的な数値目標(KPI)を設定していないため、施策がうまくいっているのかどうかの判断もできず、改善のサイクルを回せないまま時間とコストだけを浪費してしまう結果に繋がります。
3.2 原因2 プロモーションの失敗
素晴らしい商品を用意しても、その存在が現地の消費者に認知されなければ売上には繋がりません。プロモーションの失敗は、越境ECの成否を分ける大きな要因です。特に、日本国内で成功したマーケティング手法をそのまま海外で展開しようとして失敗するケースが後を絶ちません。
例えば、国や地域によって主流となるSNSは大きく異なります。日本ではLINEやX(旧Twitter)、Instagramが主流ですが、中国ではWeChatやWeibo、東南アジアではZaloやWhatsAppが広く使われています。ターゲット国で利用されていないプラットフォームで広告を出しても、効果は限定的です。
また、広告のクリエイティブやキャッチコピーを単純に翻訳しただけでは、文化的な背景や価値観の違いから、意図したメッセージが伝わらないばかりか、時にはネガティブな印象を与えてしまうことさえあります。現地のインフルエンサーを起用する際も、フォロワー数だけでなく、自社ブランドとの親和性やフォロワー層の質を見極めなければ、費用対効果の低い施策に終わってしまいます。
3.3 原因3 物流・決済システムの軽視
顧客が商品をカートに入れ、購入意欲が最高潮に達したとしても、最後の決済や配送の段階でつまずいてしまっては元も子もありません。この「購入体験」に関わる物流・決済システムを軽視することが、カゴ落ち(カートに商品を入れたまま購入に至らないこと)率を高め、売上機会を損失する直接的な原因となります。
物流面では、高額な送料や長い配送期間が大きな障壁となります。配送料が商品価格に見合わないと感じたり、商品がいつ届くか分からなかったりすると、顧客は購入をためらいます。また、関税や輸入消費税の扱いが不明確で、商品受け取り時に顧客が想定外の費用を請求されるといったトラブルは、顧客満足度を著しく低下させ、リピート購入の機会を失う原因となります。
決済面では、クレジットカード以外の決済手段が用意されていないことが致命的です。国によっては、中国のAlipayやWeChat Pay、欧米で普及しているPayPal、東南アジアの銀行振込やコンビニ決済など、クレジットカードよりも好まれる決済方法が存在します。現地の主要な決済手段を導入していないことは、販売機会の大きな損失に直結するのです。
3.4 原因4 法律・規制への無理解
国境を越えてビジネスを行う越境ECでは、相手国の法律や規制を遵守することが絶対条件です。これらへの無理解は、ビジネスの機会損失どころか、罰金やアカウント停止、さらには訴訟といった深刻な事態を招きかねません。
特に注意すべきは、輸出入に関する規制です。例えば、食品や化粧品、電子機器などは、国によって成分や規格に関する規制が異なり、販売が禁止されている場合があります。知らずに販売してしまうと、税関で没収されたり、全量返送となったりするリスクがあります。
また、商標権や意匠権といった知的財産権を販売先の国で取得していなければ、現地の業者に商品を模倣されたり、逆に権利侵害で訴えられたりする可能性があります。さらに、EUのGDPR(一般データ保護規則)に代表される個人情報保護法への対応も必須です。顧客データを適切に管理・運用する体制がなければ、高額な制裁金を科される恐れがあります。
3.5 原因5 文化・習慣の壁
法律や制度といった明文化されたルールだけでなく、現地の文化や習慣、国民性といった目に見えない壁も、越境ECの成功を阻む大きな要因です。日本人の感覚で「良かれ」と思って行ったことが、海外では全く受け入れられない、あるいは不快感を与えることさえあります。
Webサイトのデザイン一つとっても、国によって好まれる色使いやレイアウトは異なります。日本では情報量の多いデザインが好まれる傾向にありますが、欧米ではシンプルで洗練されたデザインが好まれるなど、ターゲット国の美意識に合わせる必要があります。また、商品ページの説明文や画像のモデル選定も重要です。単なる直訳ではなく、現地の文化やライフスタイルに寄り添った言葉選びや、共感を呼ぶモデルの起用が求められます。
さらに、カスタマーサポートの対応も現地の言語や時間帯に合わせなければ、顧客に不信感を与えてしまいます。ブラックフライデーや独身の日といった現地の大型セール時期を把握せず、商機を逃してしまうのも、文化への理解不足が原因と言えるでしょう。
失敗を乗り越え売上を倍増させる越境ECの成功戦略
越境EC事業が「儲からない」状態に陥ってしまうのは、決して珍しいことではありません。しかし、多くの失敗は、事前の準備と正しい戦略によって回避することが可能です。ここからは、前章で分析した失敗原因を踏まえ、それらを乗り越えて売上を倍増させるための具体的な成功戦略を4つのステップで詳しく解説します。感覚的な運営から脱却し、データに基づいた戦略的な越境EC展開を目指しましょう。
4.1 戦略1 データに基づいた販売計画の立案
越境EC成功の第一歩は、綿密なリサーチとデータ分析に基づいた販売計画を立てることから始まります。「なんとなく売れそう」といった曖昧な理由で進出先や商品を決定することは、失敗の典型的なパターンです。客観的なデータを用いて、勝算の高い市場で戦うための土台を構築しましょう。
〇ターゲット国と商品の選定方法
どの国で、何を売るのか。この最初の選択が、事業の成否を大きく左右します。ターゲット国を選定する際は、以下の要素を総合的に分析することが重要です。
まず、市場規模と成長性です。JETRO(日本貿易振興機構)が公開しているレポートや各国の統計データを活用し、自社の商品カテゴリーの市場が十分に大きく、今後も成長が見込めるかを確認します。次に、日本文化や日本製品への関心度、いわゆる「親日度」も重要な指標です。Google Trendsなどを用いて、日本製品に関連するキーワードがどの国で多く検索されているかを調査するのも有効な手段です。さらに、競合の状況、関税率、法規制なども事前にリサーチし、参入障壁が低く、利益を確保しやすい国を見極めます。
販売する商品を選定する際には、「日本で売れているから海外でも売れるだろう」という安易な考えは禁物です。ターゲット国の文化、宗教、生活習慣にマッチしているか、現地のニーズはどこにあるのかを徹底的に調査します。例えば、高品質な日本の化粧品、精巧な文房具、アニメやゲームの関連グッズ、伝統工芸品などは、海外で高い需要が見込める代表的な商品カテゴリーです。また、輸送コストや破損リスクを考慮し、軽量でコンパクト、かつ壊れにくい商品から始めるのも賢明な戦略と言えるでしょう。
〇競合サイトの分析ポイント
ターゲット国と商品が定まったら、次に行うべきは競合サイトの徹底的な分析です。現地の消費者に支持されている競合サイトは、成功のためのヒントが詰まった最高の教科書となります。
分析すべきポイントは多岐にわたります。まずは、どのような商品ラインナップで、価格設定はいくらかを調査します。自社の商品と比較し、価格競争力や品揃えの独自性をどこで出すべきかの戦略を練ります。次に、サイトのデザインやUI(ユーザーインターフェース)です。どのような写真やキャッチコピーが使われているか、購入までの導線は分かりやすいかなどをチェックし、自社サイトの参考にします。
さらに、どのようなプロモーション(セール、クーポン、SNSキャンペーンなど)を実施しているか、顧客レビューの内容、そして導入している決済方法や配送オプションまで詳細に分析します。これらの情報から、競合の強みと弱みを把握し、自社が差別化できるポイント、つまり「勝てる要素」を見つけ出すことが成功への鍵となります。
4.2 戦略2 現地に最適化するローカライゼーション
海外の顧客に商品を購入してもらうためには、単にサイトを外国語に翻訳するだけでは不十分です。その国の文化や商習慣に深く根ざした「ローカライゼーション(現地最適化)」こそが、顧客の信頼を勝ち取り、購入率を高めるための重要な要素となります。
〇Webサイトの多言語・多通貨対応
越境ECサイトにおける最も基本的なローカライゼーションが、多言語・多通貨への対応です。顧客は、母国語で情報を理解し、自国の通貨で価格を確認できるサイトを圧倒的に好みます。
言語対応については、Google翻訳などの機械翻訳に頼るのではなく、必ず現地のネイティブスピーカーによる翻訳、もしくはプロの翻訳サービスを利用しましょう。機械翻訳では、不自然な表現や誤訳によってブランドイメージを損なうリスクがあります。特に、商品の魅力や世界観を伝えるコピーライティングは、文化的な背景を理解したネイティブでなければ表現が困難です。また、ターゲット国によっては複数の公用語が使われている場合もあるため、事前のリサーチが欠かせません。
通貨対応も同様に重要です。多くの顧客は、慣れない外貨での価格表示に戸惑い、購入をためらってしまいます。サイト上で現地通貨での価格を自動表示し、そのまま決済できる機能を実装することは、カゴ落ちを防ぐ上で極めて効果的です。為替レートの変動に対応できる自動更新機能も忘れずに導入しましょう。
〇文化に合わせた商品ページ作成術
商品ページの作り込みは、売上を直接左右する重要な工程です。ここでもローカライゼーションの視点が求められます。
まず、商品写真です。起用するモデルの人種や服装、写真全体のカラートーンなどを現地の好みに合わせることで、顧客は親近感を抱きやすくなります。国によっては縁起の良い色や、逆にタブーとされる色が存在するため、注意が必要です。例えば、日本ではお祝いの色である赤が、西洋では警告や危険を意味する場合もあります。
商品説明文も、単なるスペックの羅列ではなく、現地の消費者の心に響くストーリーやベネフィットを盛り込むことが大切です。どのような課題を解決できるのか、手に入れることでどのような素晴らしい体験ができるのかを、文化的な背景を踏まえて訴求します。さらに、衣類や靴などのサイズ表記は、日本で使われる「cm」や「S/M/L」だけでなく、ターゲット国で一般的な単位(インチなど)や表記方法を併記する配慮が、顧客満足度を大きく向上させます。
4.3 戦略3 海外向けマーケティングの実行
どれだけ素晴らしいECサイトを構築しても、顧客にその存在を知ってもらえなければ売上にはつながりません。日本国内でのマーケティング手法がそのまま通用するとは限らないため、ターゲット国に合わせた海外向けのマーケティング戦略を実行する必要があります。
〇越境ECにおけるSNS活用法
現代の海外マーケティングにおいて、SNSの活用は不可欠です。ただし、国や地域によって主流となるSNSプラットフォームは大きく異なります。例えば、北米やヨーロッパではFacebookやInstagramが依然として強い影響力を持っていますが、中国ではWeChat(微信)やWeibo(微博)、東南アジアではTikTokの人気が急速に高まっています。
まずはターゲット国で最も利用されているSNSを特定し、そのプラットフォームの特性に合わせた情報発信を心がけましょう。ビジュアルが重視されるInstagramでは高品質な商品写真やブランドの世界観を伝える画像を、ショート動画が中心のTikTokでは商品の使い方や制作過程をリズミカルに紹介する動画を投稿するなど、コンテンツを最適化することが重要です。
また、現地のインフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)と提携し、商品レビューやタイアップ投稿を依頼するのも、認知度と信頼性を一気に高めるための非常に有効な手段です。
〇動画コンテンツとライブコマース
テキストや静止画だけでは伝えきれない商品の魅力を、より直感的に、そして効果的に伝えることができるのが動画コンテンツです。商品の使用感やテクスチャ、360度からのデザインなどを紹介する動画は、顧客の購買意欲を大きく刺激します。
特に中国や東南アジア市場で爆発的な人気を誇るのが「ライブコマース」です。インフルエンサーがライブ配信で商品をリアルタイムに紹介・販売する手法で、視聴者はその場で質問をしたり、他の視聴者のコメントを見ながら購入を検討したりできます。この双方向のコミュニケーションと、イベントに参加しているかのような臨場感が熱狂的な購買を生み出します。ライブコマースの実施はハードルが高いと感じるかもしれませんが、大きな売上アップが期待できる強力なマーケティング手法の一つです。
4.4 戦略4 シームレスな購入体験の提供
顧客が「買いたい」と思ってから、実際に商品が手元に届くまでの一連の流れを、いかにスムーズでストレスのないものにするか。この「シームレスな購入体験」の提供が、コンバージョン率の最大化とリピーター獲得の鍵を握ります。特に、国境を越える取引では決済と配送が大きなハードルとなりがちです。
〇海外で人気の決済方法を導入する
日本ではクレジットカード決済が主流ですが、世界に目を向けると国や地域によって好まれる決済方法は実に多様です。クレジットカードの普及率が低い国も多く、現地で広く使われている決済手段を導入していないだけで、多くの販売機会を失ってしまいます。
例えば、中国ではAlipay(支付宝)やWeChat Pay(微信支付)といったQRコード決済が圧倒的なシェアを誇ります。欧米ではPayPalが根強い人気を持ち、ドイツでは銀行振込、東南アジアではコンビニ払いや各国の電子マネー(GrabPayなど)も重要な選択肢となります。自社のECサイトに、ターゲット国で最もポピュラーな決済方法を複数導入しておくことは、顧客に安心感を与え、カゴ落ち率を劇的に改善する効果があります。
〇安心できる海外配送サービスの選び方
海外配送は、越境ECにおける最後の、そして最も重要な顧客接点です。配送料金、配送日数、そして信頼性のバランスを考慮し、最適な配送サービスを選定する必要があります。
配送方法には、日本郵便が提供するEMS(国際スピード郵便)や国際eパケット、DHLやFedExといった国際クーリエなど、様々な選択肢があります。スピードを重視する顧客向けには高価でも日数の短い国際クーリエを、コストを抑えたい顧客向けには時間はかかるが安価な国際郵便を、というように複数の配送オプションを用意し、顧客が自由に選べるようにするのが理想的です。また、荷物が今どこにあるのかを追跡できる「トラッキング機能」は必須です。追跡番号を顧客に通知することで、商品到着までの不安を大幅に軽減できます。
さらに、海外配送でトラブルになりやすいのが関税です。商品代金に関税が含まれているのか(DDP)、含まれておらず受取人負担なのか(DDU/DAP)を決済前に明確に表示することが、後のクレームを防ぐために不可欠です。信頼できる配送業者と提携し、丁寧な梱包を徹底することで、顧客に「またこのショップで買いたい」と思わせる最高の購入体験を提供しましょう。 当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
これなら始められる 越境ECの始め方4ステップ
越境ECの失敗原因と成功戦略を理解したところで、いよいよ実践です。ここでは、具体的な準備からサイト公開、運用開始までの流れを4つのステップに分けて解説します。一つひとつのステップを着実に進めることで、海外展開の成功確率を大きく高めることができます。初めての方でも安心して取り組めるよう、各段階でやるべきことを明確に示します。
5.1 ステップ1 事業計画とコンセプト設計
越境ECの成否は、この最初のステップである事業計画の精度にかかっていると言っても過言ではありません。思いつきで始めてしまうと、後々の資金繰りや戦略のズレに苦しむことになります。まずは、誰に、何を、どのように売るのか、そしてどのくらいの利益を目指すのかを具体的に設計しましょう。
〇事業の根幹となるコンセプトの明確化
最初に「なぜ海外で販売するのか」「自社の商品の強みは何か」を深く掘り下げ、事業のコンセプトを固めます。例えば、「日本の伝統技術で作られた高品質な工芸品を、本物志向の欧米の富裕層に届ける」「日本の最新ポップカルチャーグッズを、アジアの若者に向けてスピーディーに提供する」など、明確なコンセプトが後のターゲット選定やマーケティング戦略の軸となります。
〇ターゲット国と販売商品の選定
次に、どの国・地域をターゲットにするかを決定します。市場規模や成長性、日本製品への関心度、競合の状況、物理的な距離(送料)などを総合的に判断します。Googleが提供する「Googleトレンド」や「マーケットファインダー」といったツールを活用し、自社商品がどの国で検索されているかといったデータに基づいて客観的に判断することが重要です。ターゲット国が決まったら、その国の文化やニーズに合わせて、販売する商品を絞り込みます。
〇収益計画と資金計画
売上目標だけでなく、必要なコストをすべて洗い出し、詳細な収益計画を立てます。商品原価やサイト構築・維持費に加え、越境EC特有のコストである国際送料、関税・消費税、決済手数料、海外向け広告宣伝費などを漏れなく計上することが肝心です。その上で、自己資金はいくら用意できるのか、融資は必要なのかといった資金計画も具体的に策定します。
5.2 ステップ2 出店方法の選定(ECモール or 自社サイト)
事業計画が固まったら、商品を販売するプラットフォームを選びます。出店方法には、大きく分けて「海外のECモールに出店する」方法と、「自社でECサイトを構築する」方法の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の事業規模や戦略、予算に合わせて最適な方法を選択しましょう。
〇海外ECモールへの出店
AmazonやeBay、中国のTmall Global(天猫国際)、東南アジアのShopeeといった、海外で巨大な集客力を持つECモールに出店する方法です。最大のメリットは、モール自体が持つ圧倒的な知名度と集客力を利用できる点にあります。自力で集客する手間が省けるため、スピーディーに販売を開始したい初心者におすすめです。一方で、出店手数料や販売手数料が発生するほか、デザインの自由度が低く、ブランディングが難しいというデメリットもあります。
〇自社ECサイトの構築
Shopify(ショッピファイ)やWooCommerce(ウーコマース)などのECプラットフォームを利用して、独自のECサイトを構築する方法です。デザインや機能を自由にカスタマイズできるため、ブランドの世界観を表現しやすいのが最大のメリットです。また、手数料がモールに比べて安く、顧客データを直接管理できるため、長期的なマーケティングに繋げやすい点も魅力です。ただし、サイト構築の知識が必要になるほか、集客はすべて自力で行わなければならないという大きな課題があります。
5.3 ステップ3 サイト構築と各種設定
出店方法が決まったら、実際に販売の場となるECサイトを構築していきます。ここでは、海外の顧客がストレスなく買い物を楽しめるよう、言語や通貨、決済、配送といった越境ECならではの設定を丁寧に行うことが成功の鍵となります。
〇サイトの多言語・多通貨対応
ターゲット国の公用語に対応することは必須です。Shopifyなどのプラットフォームには、言語切り替え機能を追加できるアプリが豊富に用意されています。機械翻訳だけでなく、ネイティブスピーカーによるチェックを行い、自然で分かりやすい表現にすることが顧客の信頼獲得に繋がります。同様に、価格表示も現地の通貨に対応させましょう。顧客が自国通貨で価格を把握できるだけで、購入のハードルは格段に下がります。
〇海外向け決済手段の導入
日本ではクレジットカード決済が主流ですが、海外では国や地域によって好まれる決済方法が異なります。世界的に広く利用されているPayPalは、アカウントを持っているユーザーが多く信頼性も高いため、必ず導入しておきましょう。その他、クレジットカード決済のStripeや、中国のAlipay、東南アジアで普及する後払い決済など、ターゲット国で人気の決済手段を複数用意することがカゴ落ち(購入直前の離脱)を防ぐ上で非常に重要です。
〇国際配送と関税の設定
商品を海外の顧客へ届けるための配送方法を設定します。日本郵便が提供する国際スピード郵便(EMS)や国際eパケットは、比較的安価で多くの国に対応しているため、最初の選択肢として有力です。よりスピーディーな配送を求める顧客向けに、DHLやFedExといった国際クーリエも併せて用意しておくと良いでしょう。また、商品受け取り時に発生する可能性のある関税について、誰が負担するのか(DDP/DDU)をサイト上に明記し、顧客とのトラブルを未然に防ぎます。
5.4 ステップ4 集客と運用開始
サイトが完成したらいよいよオープンですが、ただ待っているだけでは顧客は訪れません。ターゲット国の顧客にサイトの存在を知ってもらい、購入してもらうための集客活動と、注文から発送までをスムーズに行うための運用体制の構築が必要です。
〇海外向けWebマーケティングの実施
前章の戦略で解説したマーケティング手法を具体的に実行に移します。ターゲット顧客がよく利用するSNS(Instagram, Facebook, TikTokなど)での広告配信や、現地のインフルエンサーに商品レビューを依頼する方法は、初期の認知度向上に特に効果的です。また、ターゲット国でよく検索されるキーワードを調査し、ブログ記事を作成するといったSEO対策も中長期的な集客のために欠かせません。
〇受注・梱包・発送のオペレーション構築
注文が入ってから商品を発送するまでの流れを確立します。受注管理システムを導入し、注文内容の確認、在庫の引き当て、インボイス(商業送り状)の作成といった一連の業務を効率化しましょう。海外発送では、国内配送以上に丁寧で頑丈な梱包が求められます。配送中の破損を防ぐため、緩衝材を十分に使い、防水対策も施します。発送後は、追跡番号を必ず顧客に通知し、商品が手元に届くまで安心して待てるように配慮することが重要です。
〇カスタマーサポート体制の準備
海外の顧客からの問い合わせに対応する体制を整えます。時差を考慮し、可能な限り迅速に対応できるよう、問い合わせフォームやメール、チャットツールなどを準備します。言語の壁があるため、翻訳ツールを活用しつつも、丁寧なコミュニケーションを心がけることが顧客満足度を高め、リピート購入に繋がります。
まとめ
国内市場の成熟化に伴い、越境ECによる海外販路拡大を検討する企業は増加しています。しかし、準備不足のままでは「儲からない」という失敗に陥りがちです。本記事で解説した通り、失敗の多くは戦略不足や現地文化への無理解が原因です。データに基づいた計画立案や徹底したローカライゼーションなど、ご紹介した具体的な解決策を実践することで、越境ECを成功に導き、売上を倍増させることも可能です。
当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
情報収集や比較検討されている方 必見!
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」
それではまた。
アンドファン株式会社
中小企業診断士 田代博之